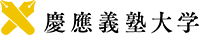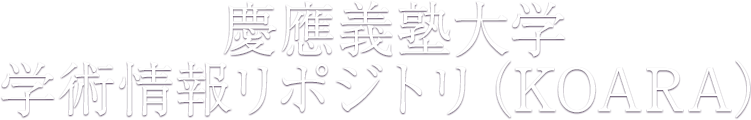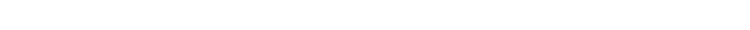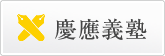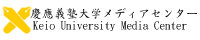| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
|
| プレビュー |
| 画像 |

|
| キャプション |
|
|
| 本文 |
2021000003-20210184.pdf
| Type |
:application/pdf |
Download
|
| Size |
:132.5 KB
|
| Last updated |
:Feb 16, 2024 |
| Downloads |
: 138 |
Total downloads since Feb 16, 2024 : 138
|
|
| 本文公開日 |
|
| タイトル |
| タイトル |
ユムシ類を中心とした海産環形動物の系統分類学的研究
|
| カナ |
ユムシルイ オ チュウシン トシタ カイサン カンケイ ドウブツ ノ ケイトウ ブンルイガクテキ ケンキュウ
|
| ローマ字 |
Yumushirui o chūshin toshita kaisan kankei dōbutsu no keitō bunruigakuteki kenkyū
|
|
| 別タイトル |
| 名前 |
Taxonomic studies of marine annelids in Japan, with special reference to the echiurans
|
| カナ |
|
| ローマ字 |
|
|
| 著者 |
| 名前 |
田中, 正敦
|
| カナ |
タナカ, マサアツ
|
| ローマ字 |
Tanaka, Masaatsu
|
| 所属 |
慶應義塾大学商学部助教 (有期) (自然科学)
|
| 所属(翻訳) |
|
| 役割 |
Research team head
|
| 外部リンク |
|
|
| 版 |
|
| 出版地 |
|
| 出版者 |
| 名前 |
慶應義塾大学
|
| カナ |
ケイオウ ギジュク ダイガク
|
| ローマ字 |
Keiō gijuku daigaku
|
|
| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2022
|
| 出版年(to:yyyy) |
|
| 作成日(yyyy-mm-dd) |
|
| 更新日(yyyy-mm-dd) |
|
| 記録日(yyyy-mm-dd) |
|
|
| 形態 |
|
| 上位タイトル |
| 名前 |
学事振興資金研究成果実績報告書
|
| 翻訳 |
|
| 巻 |
|
| 号 |
|
| 年 |
2021
|
| 月 |
|
| 開始ページ |
|
| 終了ページ |
|
|
| ISSN |
|
| ISBN |
|
| DOI |
|
| URI |
|
| JaLCDOI |
|
| NII論文ID |
|
| 医中誌ID |
|
| その他ID |
|
| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
|
| 学位授与年月日 |
|
| 学位名 |
|
| 学位授与機関 |
|
|
| 抄録 |
本研究の目的は、ユムシ類を中心とした海産環形動物の分類学的研究を実施することで、海域の底生生物群集において重要な位置を占める環形動物の生息状況や絶滅のリスクを定量的・定性的に評価するために不可欠な、生物多様性情報の集積とその基盤を確立することである。当初の計画では、国内での野外調査と国内外の博物館標本調査を実施する予定だったが、いずれも調査の実施予定時期と新型コロナウイルスの変異株の蔓延期間が重なったため、断念した。そのため、国内外の関連文献を網羅的に収集し、その解読と各文献に含まれる環形動物の生物多様性情報の抽出と整理作業に多くの時間を割いた。また、研究を通じて見出された、深海性ボネリムシ類3属の著者権に関する命名学的問題、そしてホシムシ類の古典的モノグラフ「Die Sipunculiden」の出版年ならびにそこに含まれる学名の公表年に関する問題を解決するべく、情報収集と論文執筆を進めた。このほかに、以下の4つの成果を挙げた。
1)2020年6月から9月にかけて大阪湾奥部で採集されたユムシ類9個体が、国内では2002年以来の記録となる外来種ミナトタテジマユムシであると同定されたため、本種の新たな形態学的知見と併せて学会発表を行った。
2)2013年に新種記載されたのち、ほとんど記録がなかったセトウチドチクチユムシについて、2013年~2020年の間に採集された新規標本ならびに博物館所蔵標本の検討結果に基づき、本種の新たな国内産地4箇所について学会発表を行った。
3)2020年6月に鹿児島県出水市高尾野川河口干潟から採集されたユムシ類1個体の標本の検討を行った結果、ユメユムシと同定されたため、本種の国内南限記録として報告した。
4)おもに2021年7~9月の間に広島県竹原市ハチの干潟およびその周辺地域で採集された環形動物標本の検討を行い、日本初記録1種と県内初記録1種を含む計22種を同定した。各種について書籍中の解説を執筆した。
The purpose of this study is to conduct a taxonomic study of marine annelids, with a special focus on echiurans, in order to establish a solid basis for quantitative and qualitative assessment of the current status of extinction risk of these animals in Japan. The initial plan included conducting field surveys and visiting museums and surveying specimens there, but both were abandoned due to the spread of the new strains of the SARS-CoV-2. Therefore, I devoted much of my time to collecting the literature related to annelids and extracting and organizing the biodiversity information contained in each literature. In addition, I am in preparing two papers to solve the nomenclatural problems of the authorships of three generic names of deep-sea bonelliids and the date of publication of the scientific names originally proposed in the classical monograph on sipuculans, "Die Sipunculiden" during 1883 to 1884. From April 2021 through March 2022, I published two original papers, wrote brief accounts for 22 species of annelids in a book (to be published), and gave two conference presentations.
|
|
| 目次 |
|
| キーワード |
|
| NDC |
|
| 注記 |
|
| 言語 |
|
| 資源タイプ |
|
| ジャンル |
|
| 著者版フラグ |
|
| 関連DOI |
|
| アクセス条件 |
|
| 最終更新日 |
|
| 作成日 |
|
| 所有者 |
|
| 更新履歴 |
|
| インデックス |
|
| 関連アイテム |
|