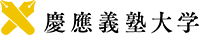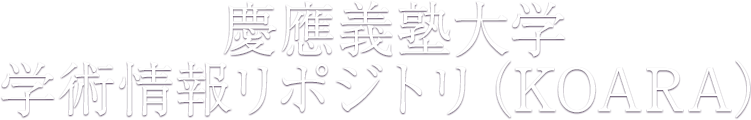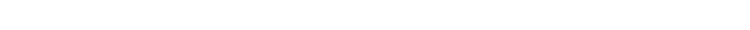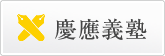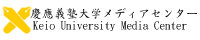本研究では、主に、外国判決が不承認となった場合に、その外国判決に基づいてすでに外国で執行等がなされていることに対して、内国で不当利得返還請求訴訟を提起することが認められるのか否かを検討した。
このような事態が生ずる一つの例として、国際的訴訟競合がある。外国で給付訴訟が提起され、他方国内で債務不存在確認訴訟が提起された場合に、この並行訴訟が解消されずに双方の訴訟につき請求認容判決が下されると、同一の当事者に対して、外国では支払義務が認められ、国内では債務不存在が認められる。この場合に、外国で強制執行された外国訴訟の被告が、内国で不当利得返還請求訴訟を提起することが考えられる。別の例として、懲罰的損害賠償を命ずる外国判決の扱いが考えられる。懲罰的損害賠償を命ずる外国判決に基づいて外国で強制執行が実施された場合に、填補賠償を超える分について、不当利得返還請求訴訟を認めるのか問題となる。コモンロー諸国でもイギリスなどは、いわゆるクローバック条項を設けて取戻を制定法で認めている。わが国では、このような制定法がないため、不当利得返還請求訴訟を提起する方法が考えられる。
この問題については、日本ではほとんど議論されていないため、本研究ではドイツでの学説・判例を紹介し、検討を試みた。ドイツでは不当利得を認めない見解が有力に説かれている。この見解は、判決の国際的調和を背景に、自然債務であることなどを理由とするものである。しかし、外国判決が内国で承認されない以上は、外国債権者は少なくとも内国においては、(部分的な場合も含めて)権利者と評価することはできないし、また、このような場合に個人の権利保護追及の手段を当初から閉ざすべきではないと考える。本研究では、このように不当利得を認めることを前提に、国際裁判管轄、準拠法決定の方法、そして具体的に準拠法となる日本民法の解釈について検討を試みた。
This study focuses on the issue that whether an action based on the unjust enrichment is admissible in Japan, if the foreign judgment had already been executed in a foreign country, but the judgment was not recognized in Japan.
One example of such situation is "concurrent actions in international civil procedure": an action for payment is brought in a foreign country, and meanwhile, an action for declaratory judgment of the absence of obligation is brought in Japan. If such concurrent actions between two countries aren't resolved, two contradictory judgments could be declared. In that case, the defendant in the foreign proceeding would bring an action for unjust enrichment at a court in Japan. Another example is related to the "punitive damages" in common law countries: if "punitive damages" judgment is executed in a foreign country, should an action for the payment of the amount exceeding compensatory damages be admitted? Many common law countries have "claw back provision" in blocking statutes, but there is no such provision in Japan.
Since this theme is seldom discussed in Japan, I reviewed mainly the literatures and judgments in German. The prevailing view in Germany is to deny the action based on the unjust enrichment because there is natural obligation. This interpretation exists in the background of international harmonization of judgments. However, I am against this opinion. When a foreign judgment is not recognized in Japan, the creditor by the foreign judgment is not – as a whole or partially -- entitled in Japan. Moreover, an individual who pursues his/her right should not be turned away without adequate judicial proceeding. I studied the interpretation of the international jurisdiction, conflict of laws, and civil law in japan, on the premise that unjust enrichment action should be admissible.
|